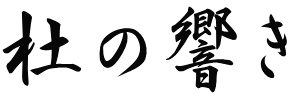|
「杜の響き」メッセージ 第56章 平成から令和への御代替わりに伴い諸儀式が粛々と進められています。中でも広く 全国を対象に祝意の対象として執り行う大嘗祭は、農耕民族が自然界に謝意を込めて 発祥した行事であり、先の大戦後にも勤労感謝の祝日として存続させた経緯からも意 義深い神事と存じます。 大嘗祭の主幹は神饌としての新穀です。 去る5月13日「斎田点定の儀」が催され、祭礼に供えられる新穀の斎田が古式に 則り亀卜を以って、悠紀斎田:栃木県主基斎田:京都府の地域に定められました。 今後この地域より斎田が選ばれ「地鎮の儀」「抜穂の儀」「大祓い」を経て秋の収 穫期には脱穀し献納に至ることとなります。 従来弊社境内には「天武天皇悠紀斎田跡」(愛知縣)の碑があり、第40代天武天皇 の御代(673~686)に当澁川地区の田圃で悠紀斎田(尾張は都の東側に当たり 悠紀を採用)が選定された旨の表示があります。 飛鳥時代後半に壬申の乱を経て即位した天武天皇(大海人皇子)は従前の新嘗祭に 殊の外関心を抱かれたようです。 往時からの地元伝説にもこの度と同じく亀卜による選定とあり、令和への改元に当 たっても同様の儀式が報道され伝統の重みを感じています。 大海人皇子は流行りの 中国の占術「遁甲」を背景に古来の「亀卜」を採用したと考えます。 小生が幼少期世話になった旧澁川国民学校(後小学校に改称)の校歌にある「天武の 御代の悠紀の田の、ゆかりかしこき学び舎に、祖先のほこりいかすべき、われらの血潮 たぎるなり」を繙き、天武の御代替わりに合わせて社殿の遷宮がなされた事、新穀献納 後の直会会場に建立された直會神社等1300余年に遡る伝統を礎に、都市化されたとは 言え悠紀斎田の史実を神社存続と共に継承したく思います。 令和元年 6月 1日 「杜の響き」 森下千晴 記 杜の響きへ続く 神社INDEX |