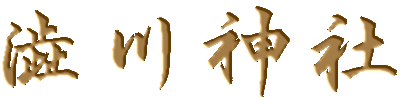
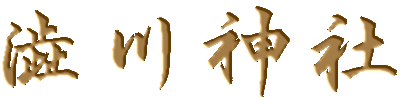
| 古くは延喜年間(西暦929年)には式内社に撰進され「山田郡の総鎮守」として、朝廷からの幣帛も授かる存在となり 約四百五十年前武将織田信長が本殿を改修、貞享五年には尾張藩主徳川光友により本殿が改築される等、史上の著名人にも 崇敬された由緒ある神社です。 |
| 澁川神社 各種祈願・厄祓いなど 初宮詣り 七五三詣り 厄除祓い 心願成就 学業成就 合格祈願 健康長寿 勝運向上 家内安全 安産祈願 交通安全 車御祓い 結婚式 各種祈願・ご祈祷 昇殿参拝 地鎮祭・入居祓い 忌年祭等(出張祈願)等、承っております。社務所にご相談ください。 |
| 「手水、拝礼、玉串」の3つに分けて、簡単に要領よく説明させて戴きます。 神社や家に祀られている神棚などを通して、身近な所で一度試してみてください。 |
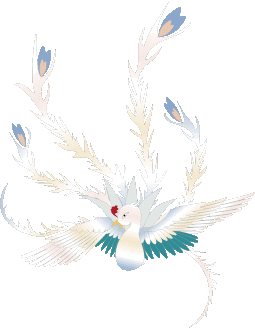 |
 澁川神社では、ニ礼二拍一礼です |
 |
|---|
| ここでは、神社での参拝の作法を紹介させて戴きます。 参拝については、多くの方が作法として正しく身につける機会が少なく見よう見まねで、覚えている方も多いと思います。 学校での指導は当然ありませんから、経験ある家族などから、学ぶことが良い方法だと思います。 手水、拝礼、玉串の3つに分けて、簡単に要領よく説明させて戴きます。神社や家に祀られている神棚など通して、身近な 所で一度試してみてください。ご希望の方は正しい参拝の作法など、お教え致します。 参拝の作法は、単なる作法ではなく、この作法を通して、人としてとても大切なことを学ぶことができます。 説明順 1.手水の作法、 2.拝礼の作法、 3.玉串の作法 |
|---|
 |
鳥 居 ・神社参拝の第一歩は鳥居からです。鳥居は神域の入り口を示します。 ・鳥居の左か右端に立ち、軽く会釈をし気持ちを引き締めてからくぐりましょう。 ・鳥居から社殿にいたる参拝の道筋を参道といいます。 ・真ん中は神が歩かれるとされていますので、端を歩くことをお勧めします。 ・御帰りの際に鳥居の両端に立ち、軽く会釈をして御帰りになると、神様への感 謝の気持ちで満たされると思います。 |
|---|
大鳥居を入って右手 「手水舎」 |
澁川神社の手水は地下水で奇麗な御神水です。 いつも清潔に維持管理がされて、総代の皆さん で、守られています。 |
|---|
1.手水の作法 「手水」は「ちょうず」「てみず」と読みます。 神社の入り口付近には手水舎 (ちょうずしゃ・ちょうずや・てみずや・おみずや)があります。 神前に立つ前に手を洗い、口を漱いで身と心を清めましょう。 |
|---|
| ① まず、右手で柄杓を取り、左手を洗います |
柄杓に口をつけてはいけません |
|---|
| |
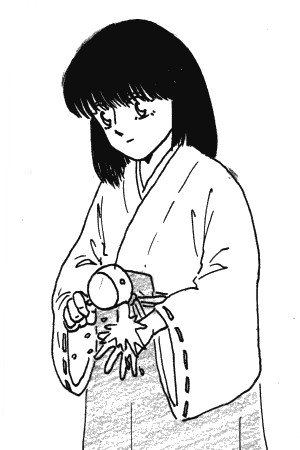 |
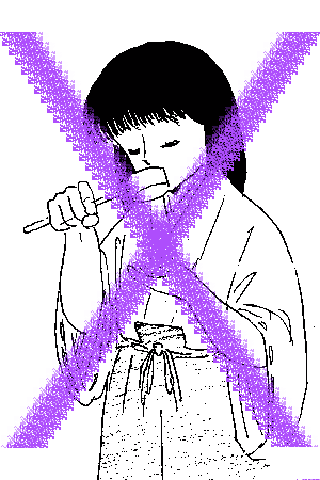 |
|---|
② 次に、左手に持ち替えて、右手を洗います。まず、右手で柄杓を取り、左手を洗います |
|---|
 手水作法に慣れた総代さん |
 作法が美しい人の皆さん |
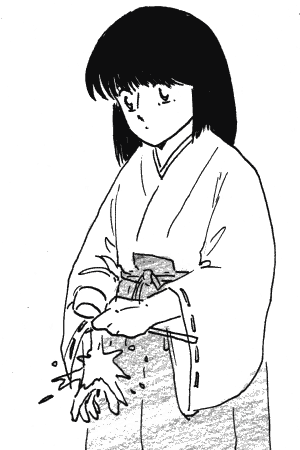 |
|---|
⑤ 柄杓を立てて、柄に水を流します。 |
⑥ 柄杓を元の場所にふせて置きます。 |
|---|
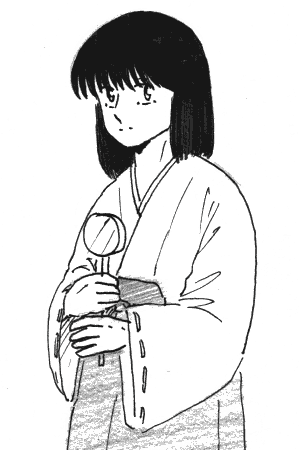 |
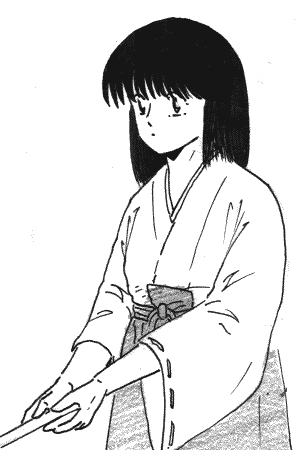 |
手水作法のまとめ 杓手水作法の後にハンカチ等で 濡れた手と口の周りを拭くと作 法が綺麗にまとまります。 |
|---|
2.拝礼の作法 拝殿に向かう心得」 澁川神社での拝礼の基本は二拝二拍手一礼です 手水で心身ともに清めてから、神前に向かいます。 この時参道の中央は避けて通ります。 中央は「正中」と言って、神様の専用通路になっています。 拝礼の基本は「二拝二拍手一拝」ですが、例外(出雲大社等)もあります。 |
 |
|---|
① 軽く会釈をします。賽銭を投じ、鈴を鳴らします。 |
|---|
澁川神社 拝殿 |
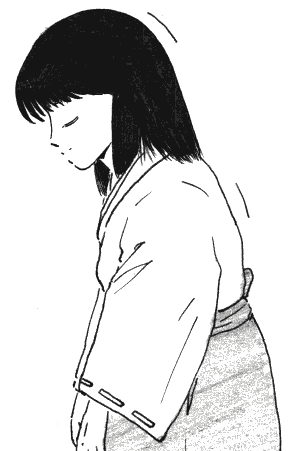 |
|---|
② 頭を深く二回下げます(二拝)腰から深く曲げましょう。 |
|---|
 澁川神社 本殿 |
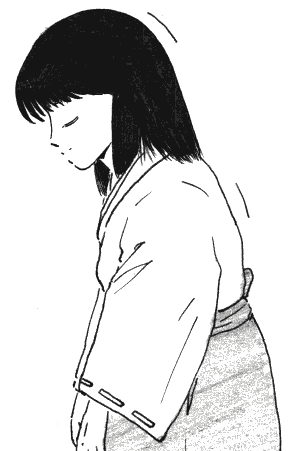 |
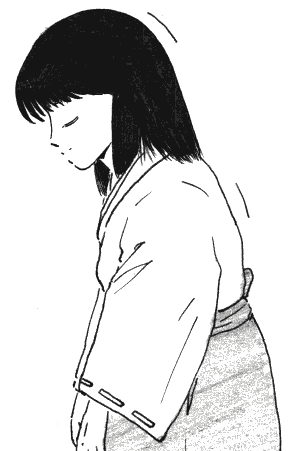 |
参拝者の美しい拝礼 |
|---|
③ 手を合わせます。 右の掌を左に対して少し引きます。 柏手(かしわで)を 二回打ちます(二拍)。 続いて、祝詞(ノリト)・略拝詞 (リャクハイシ)・祈願等を行います。 |
④ もう一度、頭を深く下げます(一拝)。 今度は一回。 |
|---|
 拍手を打つ手先 |
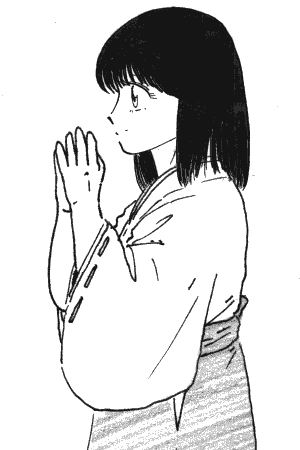 |
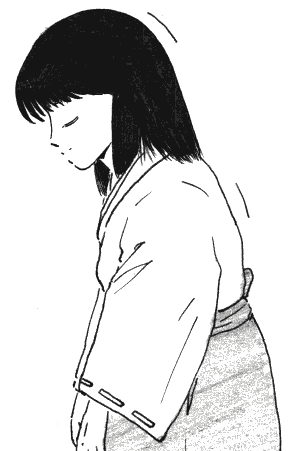 |
|---|
3.玉串の作法(玉串奉奠) <玉串について> 正しくは「玉串を奉りて拝礼」といいます。 玉串とは霊串のこと。 榊の小枝に祈る人の霊を込めて神にささげます。 |
 |
|---|
① 右手で榊の元の方を上から持ち左手で先の方から支え ます。位置は胸の高さ、左手の枝先を上にします。 |
② 玉串案(机)の前三尺(約90cm)ほどの所で止まり 揖(シンユウ)します。深揖とは=正式には腰を90度 に曲げて深い会釈をするが、略式として、45度で行わ れる事もある。 |
|---|
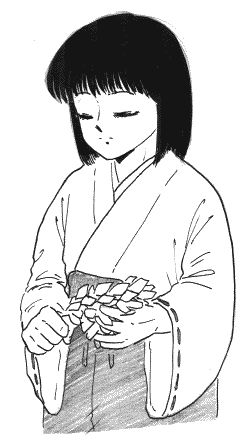 |
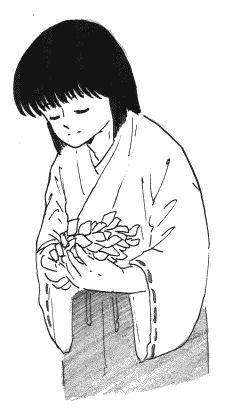 |
|---|
③ 玉串を時計回りに90度回転させます。 今度は左手で元の方を持ち、右手は先に添えます。 元の方を下げた形で祈念をこめます。 |
④ 同じ方向にさらに180度回転させます。 右手で榊を支え、左手は右手の下に添えます。 |
|---|
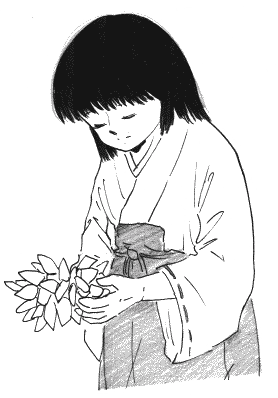 |
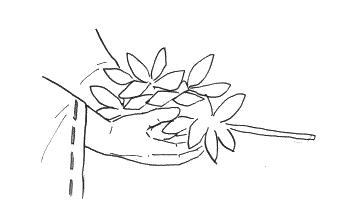 |
|---|
| ⑤ やや進んで、榊の元の方を神前に向けて案 (机)の上に置きます。その後、やや退きます。 |
⑥ 「二拝二拍手一拝」します。 |
⑦ 再度深揖して自席に戻ります。 |
|---|
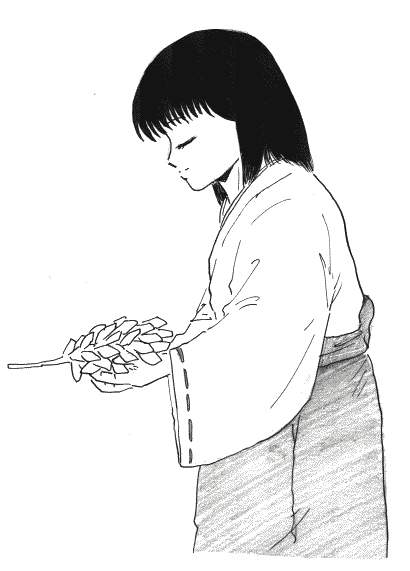 |
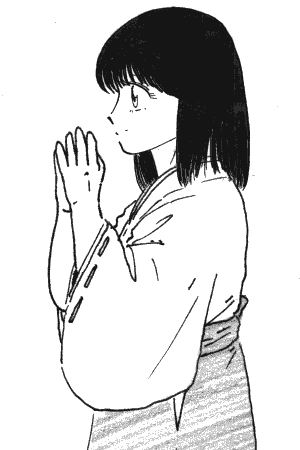 |
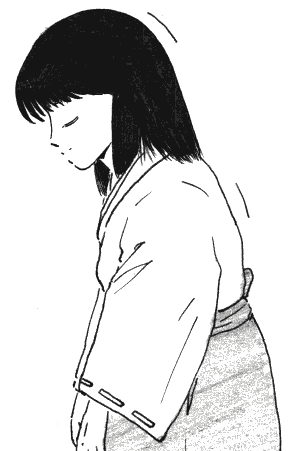 |
|---|